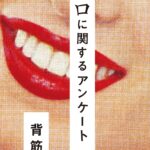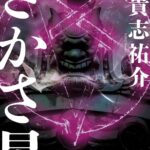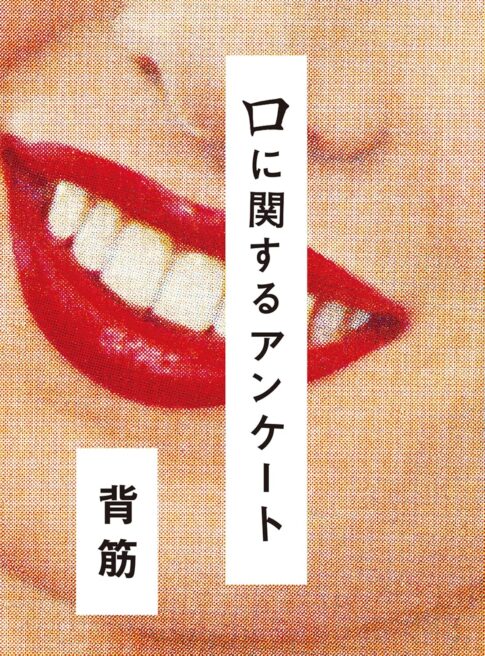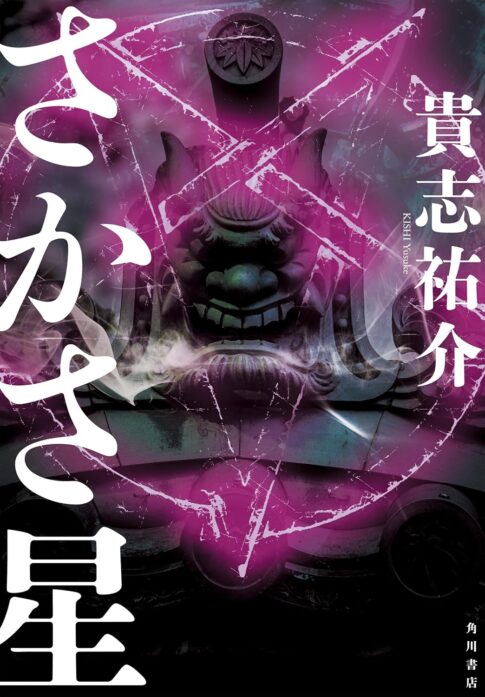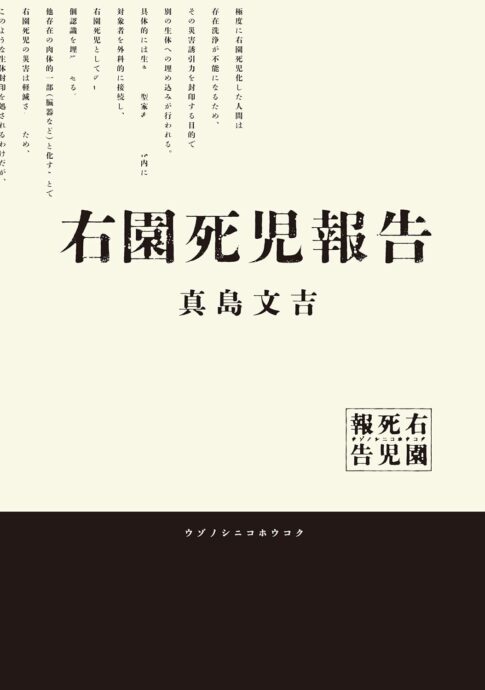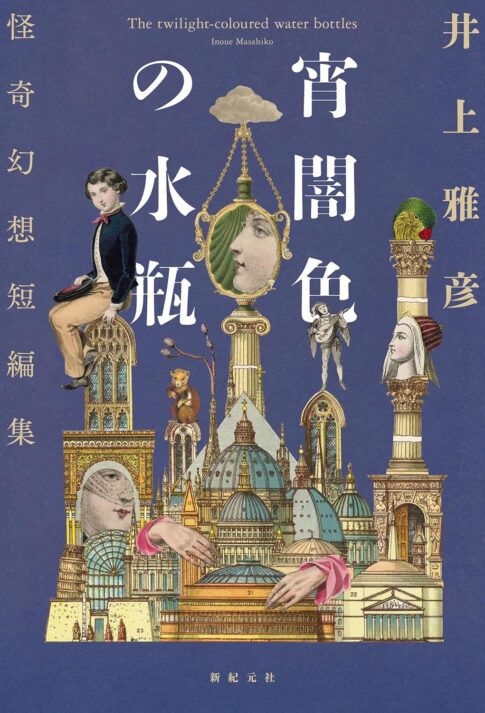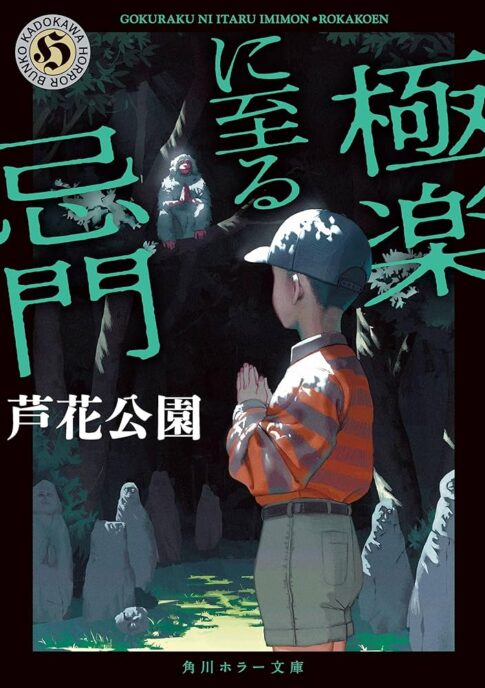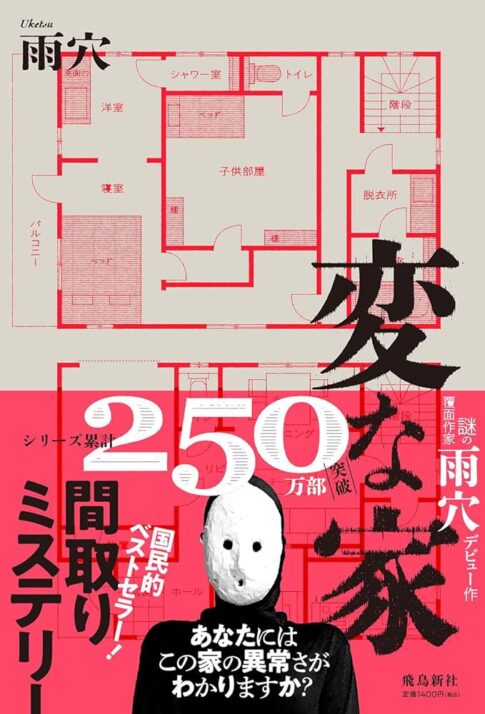【書籍レビュー】『骨を喰む真珠』――大正大阪に潜む怪薬と、死者の声を呼ぶ真珠の恐怖
作品概要
北沢陶による『骨を喰む真珠』は、「このホラーがすごい!2025年版」で国内編第3位にランクインした注目作です。
舞台は大正時代の大阪。都市近代化の喧騒の中に広がる裏社会を背景に、不審な丸薬と不気味な真珠をめぐる怪奇が描かれます。
作者は歴史的資料と幻想文学的手法を巧みに融合させ、実在感と幻想の境界を揺らすスタイルで読者を魅了しました。
あらすじ(ネタバレなし)
主人公は新聞社に勤める若き女性記者・多佳。
彼女は街で流行する「奇妙な丸薬」に関する記事を任されます。その薬は飲むと体調が良くなると噂される一方、服用者の間で怪死事件が相次いでいました。
調査を進めるうちに、多佳は「骨を喰む真珠」と呼ばれる宝飾品の存在に行き当たります。
その真珠は薬の原料とされ、さらに“死者の声を聞かせる”という不気味な伝承を持っていました。
薬、真珠、そして背後に蠢く組織の陰謀が絡み合い、彼女は恐怖の深淵へと足を踏み入れていきます。
恐怖の仕掛け
本作の恐怖は「薬」と「宝飾品」という、日常に身近なものから生まれる点にあります。
それらは本来、人を癒やし、飾り立てるためのもの。しかし『骨を喰む真珠』では、それらが逆に人を蝕み、命を奪う存在へと反転します。
- 薬の不気味さ:丸薬は「効能がある」とされながらも、どこか説明のつかない恐怖を呼ぶ。
- 真珠の象徴性:死者と交信するかのような“骨を喰む真珠”が、装飾品の美しさと恐怖を二重化。
- 都市の闇:近代化の裏に潜む人間の欲望が、恐怖を現実的に補強する。
読後感と意義
読後に残るのは「大正という時代が孕んだ不穏さ」です。
新しい文化が流入する一方で、迷信や闇医療が根強く残る時代背景。その曖昧さが、恐怖を増幅させています。
北沢陶はその時代の匂いや街並みを緻密に描写することで、読者をリアルに引き込み、そこで生まれる恐怖を“まるで実際に体験したかのように”感じさせてくれます。
『骨を喰む真珠』は、怪奇ミステリでありながら、社会派小説としての側面も持っています。
「薬を信じたい」「美しいものに惹かれる」という人間の欲望が、怪異と結びつくことで悲劇を生む――その構造は、現代社会にも通じる警鐘を含んでいます。

「薬と宝石が恐怖の源になるなんて思わなかった…。身近なものが一番怖いのかもしれない」

「真珠って本来は美の象徴なのに、“骨を喰む”なんて逆転した意味を与えられると不気味さが倍増するわね…」
© 2025 こわ!ブロ All Rights Reserved.